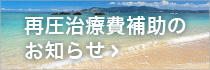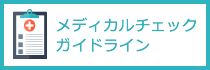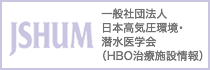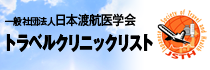アドバンス講習中のダイバーが、浮き気味で悪戦苦闘
担当インストラクターはトラブルに気づかず、解決することができなかった
[報告されたケース]
20本ほどのダイビングを経験した後、クルーズ乗船中にPADIのアドバンスコースを受けることにしました。今まで、さまざまな条件に合わせて5mm・7mmのウェットスーツ、またはウェットスーツを着用しないダイビングなど経験してきました。また、使用したウェイトは毎回記録し、ウェイトが足りなかったり、重すぎたり、という経験はありませんでした。
その日、私は3mmのウェットスーツを着用してダイビングをしました。1本目のダイビング後、担当インストラクターにウェイトが足りないようだ、と伝えました。水深15mでもBCDの空気を完全に抜かないと浮いてしまい、水深4mで安全停止する際には、背中を反らしてフィンで下向きに泳がないと止まることができませんでした。
この状況を担当インストラクターに詳しく伝えましたが「ダイビング中を通して浮力に問題はなかった」「もしウェイトを追加したらオーバーウェイトになる」と言い張るのです。彼女は、自分は正しいウェイトを付けさせる達人だと言っていました。
その後、私は2日間の講習で5ダイブを修了しました。水深約15mより浅いところでは、下向きに泳ぎ続けなければならず、毎ダイブごとに腰が痛くなりました。今思い返せば、もっとウェイトを付けたい、と私が主張すればよかったのです。でも、インストラクターから「早くして」というプレッシャーを感じ、私は今まで自分のスキルに自信を持って潜ってきたのですが、自分が本当に正しかったのかすら判らなくなってきてしまいました。
また、担当インストラクターに「浮力チェックは必要ないから、潜降を開始してください」と言われ、浮力チェックをする機会も与えられませんでした。私は、担当インストラクターが、計画された出発/到着時間を守るためにダイビングをしようとしているようだ、とツアー中ずっと感じていました。
[専門家からのコメント]
適切な浮力コントロールは、楽しく安全なダイビングに欠かせません。
浮力コントロールのスキルは、ダイバーのトレーニングレベル、およびダイビングの熟練度を最もよく示すものです。しかし、経験豊富なダイバー(インストラクター)でも、浮力チェックせずにダイバー1人1人の最適ウェイト量を確実に推測することはできません。潜降前に水面で実施する浮力バランスのチェックは、ダイビング前チェックの標準的な手順の1つであるべきです。浮力チェックを実施しない場合にはダイバーがトラブルに遭遇する危険性がありますし、浮力チェックを要求しないのはインストラクターの不注意と言えるでしょう。このダイバーは浮力コントロールの重要性を理解し、浮力チェックを実施したいと考えていたにも関わらず、インストラクターに聞き入れてもらえなかったようです。
初心者ダイバーが、担当インストラクターの忠告に逆らってでも自分の安全に責任を持つ、ということは難しいことです。しかし、インストラクターは自分の顧客に対する安全管理責任はありますが、一般的には自身の安全管理に対する責任は、ダイバーにあるということに注意してください。自身の安全が好ましくない状況だと感じたら改善を求め、もし改善されなければダイビングを中止する最終的な責任は、ダイバー自身にあるのです。
– Petar Denoble, MD, DSc.
【関連記事】ウェイトが軽すぎて不快なダイビングに(リンク)
→適切なウェイト量を確認するための浮力チェックの方法など