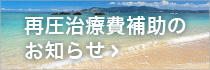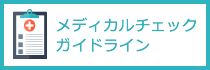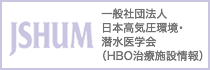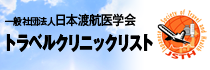原文はこちら:【CPR and COVID-19】
無症状の人でもウイルスを運搬して拡散する可能性があるため、居合わせた人が介入してCPRを行う際に、ウイルスに感染するリスクを判断することはほとんど不可能です。
居合わせた人が救急医療サービスを要請することしかしない場合、傷病者が生存する可能性は非常に低くなるでしょう。しかし、介入によって生存の可能性は大幅に改善されるでしょう。とはいえ、救助者が新型コロナウイルス感染症に曝露されるリスクも増大するでしょうから、結局のところ、行動するかどうかの決定は困難で個人的な判断となります。介入する必要があると判断した場合は、次の手順を実行することをお勧めします。

1. まず救急医療サービスを要請し、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、その疑いを伝えます。脈拍と呼吸を評価する際には、すばやく胸部の動きと皮膚と爪床のピンク色(“ピンク”は肌の色に関係なく使えます)かどうか正常な呼吸があるかをチェックします。耳や頬を相手の口に近づけないでください。²
2. CPRを行う必要がある場合は、適切な個人用保護具(PPE)を確実に用意してください。これには手袋、保護眼鏡、フェイスマスク、ガウン(利用可能な場合)が含まれます。1,3
3. 疾患が感染するリスクがあると思われる場合は、胸骨圧迫のみのCPRが成人の標準的な手順となります。感染のリスクがあると判断され、胸骨圧迫のみのCPRを行う場合は、傷病者の鼻と口にフェイスマスクまたは布(バンダナ、Tシャツ、タオルなど)を当ててください。1,2
こうすることでCPRの際に飛沫が飛び散るのを軽減することができます。
4. ポケットマスクまたはバックバルブマスク(BVM)があるなら、これらを使用するとよいでしょう。可能であればBVMには呼気用の高効率微粒子空気フィルター(HEPAフィルター)を装着すべきでしょう。1,3
ポケットマスクを使用する場合は、マスクをゴムひもで所定の位置に固定するようにしてください。4
5. 処置が終わったら適切な消毒剤を使用してその場所を清掃し、手を隅から隅まで洗います。顔を触らないようにして、家に帰ったらシャワーを浴びたり、服を洗ったり、靴を消毒することを考えてください。
CPRを必要とする小児では、胸骨圧迫と人工呼吸を行うのが最善の方法です;小児の心停止の最も一般的な原因は、窒息や溺水などの事象に起因する呼吸困難であるためです。しかし、ポケットマスクやBVMなどの適切なバリアがなくても、胸骨圧迫のみのCPRを行うことができます。4
心臓が止まった小児や乳児のほとんどは、家族や友人からCPRを受けます。もしあなたがその子供と無関係であれば、人工呼吸をするかどうか自分で決める必要があります。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中でも、AEDの使い方は変更されていません。AEDは、こうした緊急事態が生じた場合には、できるだけ早く使用すべきですが、その際には、あなたのうけたトレーニングに従って、またAEDの指示の通りに行ってください。
1 https://professional.heart.org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_505872.pdf
2 https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/covid-community/
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
4 https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/community-faqs_pediatric-covid19-and-cpr.pdf?la=en&hash=ED782EA0B970C0514AC2C59A8F11578A3047D8D2